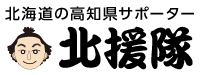シリーズ連載 [No.3]「武市安哉の軌跡」
「浦臼町史」(平成12年3月31日発刊)より
シリーズ連載1・2では、坂本龍馬の甥、坂本直寛の北見への入植活動を中心に、人となり、信条等を北見市のご理解の下、北見市史より転載をさせて頂きました。
高知県と北海道とのつながりは、坂本直寛が北見への入植する明治三十年より以前、直寛より6つ年長の、高知県議、代議士としてまた自由民権運動の同士として尊敬していた、現南国市出身の武市安哉(たけち あんさい・やすや)が先に樺戸郡浦臼町に入植したことに遡ります。
シリーズ連載3では、その武市安哉の軌跡を、浦臼町のご理解を頂き、「浦臼町史」(平成12年3月31日発刊)より「第3節 聖園農場 を転載させて頂きます。
お楽しみ下さい。ご通読頂ければ幸いです。
- 第一話
第3節 聖園農場
北海道土地払下規制時の団体移民に、キリスト教系集団が目立っている。
同志社系信者学生と聖公会系が共同した檜山支庁管内今金町のイマヌエル(現在神丘)と、代議士を辞した高知の武市安哉が率いる浦臼町聖園がそれである。また、キリスト教系の集団ではないが、富山県郡から集団移民した栗沢町砺波部落は、郷里から神社・寺を持ち込んで、郷里との連続と精神統一をはかったものである。(『新北海道風土記』より)
この聖園農場は、現在移住当時の農場の規模、内容とはすっかり様変わりした形で、その名前を残し、当時、創建した「聖園教会」が100年を経た今日も、その精神を継いで教会として活動を続けている。
安哉の生いたちと投獄
弘化4年(1847)、高知県長岡村(現南国市大篠村)に生まれた安哉は、12歳の時父を失い、農耕に精を出して母を助けた。15歳の時、郷士の本家を相続したが、住吉野では郷士を含めて地主が2、3戸あるほかは小作人ばかりで、しかも一戸当たり4反歩ほどにすぎないので、次男や三男に土地を分けてやることもできなかった。おまけに、収穫の半分以上が小作料やその他にかかり、いつまでも希望のない生活から抜け出せない人たちを見つめながら育ったのである。
明治になって、武家政治が廃止されて市民平等とはなったものの、明治6年の地租改正では負担が軽減されないばかりか、滞納すれば土地まで取り上げられ、物納が金納に変わったため、米は商人に買い叩かれた。この生活苦からいたるところに一揆や騒動が起きた。このような状態を目のあたりにして、安哉は学問に対する態度が真剣になり、新しい知識を得るため東京や大阪に出かける回数が多くなった。
こうして、安哉は地域でただ一人の物識りとなり、26歳で村の小学校の教師となったが、明治7年には大埇村を含む小区の区長となり、翌年に大区制ができると大区長に選ばれたのである。
高知県会が開設されたのが明治12年(1879)で、安哉は、県会議員となり、板垣退助を総理とする自由党員として、租税軽減、言論集会の自由、外交の挽回について建白運動を続けた。ところが、にわかに発布された保安条例に触れて石川島監獄に投ぜられた。
軽禁錮2年6か月、監視2年の刑を受けたのである。つづく
- 第二話
洗礼後、安哉の心境の変化
安哉は明治18年にキリスト教の洗礼を受けている。信仰に入った動機の一つには、これからの日本の政治は西欧に学ぶことの多いことと信じたからであろう。明治23年2月、憲法発布の大赦で出獄した安哉は、再び各地を講演して歩いたが、その頃から同志の人たちが口にする「食わず民権から食える民権へ」ということばを真剣に考え始めていた。
第1回国会議員選挙は明治23年7月に行われたが、翌年12月26日に解散、次に行われた25年2月15日の総選挙に安哉は党と地元から推されて国会議員に当選した。しかし、民権運動とキリスト教の中で成長してきた安哉には、国民から離れた議会や利権と打算で離散集合する党人が汚いものに見えて仕方がなかった。議会がすんで故郷に帰ってみると、農村はますます苦しくなっている。12キロメートル離れた高知の町へ、1駄40束の大根を持って行くのだが、10本1束で5厘にしか売れない。「夕方、売れ残ったやつは3束で1銭ですから涙が出ますよ」と農民がコボスのも無理はなかった。破産して村を去る者、都会へ出て労働者になる者が絶えない。生まれた子供を窒息させて死なせる因習が、まだ残っているのか、日本全体の人口は1年間に40万人も増えているのに、故郷の住吉野は20年このかた、かえって人口は減っていた。
ある夜、安哉は妻のシカと話し合った。シカは30年近い年月を夫と苦難を分ち、愚痴ひとつこぼさない女性であった。「何ごとも神様のおぼしめしと存じます。お気にせられず、あなたがなさりたいと思うようになさいませ。これからも、私たちのいたしますことが、もし神様のみ心に叶うものでしたら生活のみちは何とでも開けてまいりましょう」ふだんを、子供を育て家事に追われている妻が神と夫を信頼して力強く励ます言葉に安哉は新しい光を得る思いであった。
つづく
- 第三話
北海道視察の途中 移住決意
たまたまであったが、明治25年、東京の党本部から開拓地の払下げ問題を調査するため、北海道へ出張の依頼を受けた安哉は、この時とばかり胸をはずませた。北辺の資源開発に力を入れた開拓使は、12年半続いて廃止され、代わって設置された「3県1局制度」も4年で終わり、その時は、北海道庁が移民奨励と開発促進に力を入れていた。
資力ある者は、広い土地の払下げを許され、すでに石狩の南部は大体拓かれて、開拓の精神がみなぎっていた。しかし、中には利権目あてに大土地を手に入れる者もあって、社会の疑惑を生み、国会の問題にもなっていた。安哉が出張してきた目的は、これらの実情を調べることにあったのである。
こうして渡道してきた安哉は、北海道の調査によって別な感銘を受けたのである。右を見ても、左を振り向いても山ばっかりで鼻のつかえる故郷の土佐とくらべて、目の届く限り続く原生林と未開の草原は、安哉の心を大きく揺り動かした。ホーレス・ケプロンをはじめ、北海道開拓に貢献した多くの事がら、特に札幌農学校の初代教頭ウイリアム・スミス・クラークが青年い残したことばは安哉を感動させた。こうして調査を進めているうちにしだいに、故郷の貧しい人たちを移住させて理想の村を建設する決心を固めていったのである。さっそく、時の北海道庁長官北垣国道を訪れて、土地の選定を相談した。幸いに長官は、かって高知県知事を務め、互いに知る仲であったから、「岩見沢から奥へ行かなければならんでしょう。一応現地を廻ってみてはどうですか。石狩川の右岸でしたら案外あるかも知れませんよ」と言ってくれた。
土地は幾らでもあるが、適地となると難しい。長官のことばに従って、岩見沢の次の峰延で下車した安哉は、石狩川を渡って月形村の樺戸集治監を訪れた。
そこには、かねてから名を知っていたクリスチャンの原がいて、安哉のもくろみを聴き、すぐさま典獄の大井上に引き会わせ、農事指導員の小野田卓彌を加えて相談に乗ってくれた。この相談の結果、16キロメートル上流にある集治監用地の浦臼内を開放してもらってはどうかということになり、翌朝、安哉は小野田の案内で検分に出かけた。
集治監の囚徒がつくった増毛街道を乗馬で行くと、昼前に浦臼内の入口にある札的に着いた。水のきれいな川が流れていた。近くに1軒の空小屋があった。旅人のために建てた「助け小屋」である。地図で小野田農事指導員の説明を聞いた。
地形は、隈根尻山から延びてきた浦臼山を後ろにして、東部に広がり石狩川に接している。
北寄りに山地があるほかは、いくらか高知で平坦で、ところどころに小さな流れもあるから灌漑の便もよい。クルミ、ナラ、カツラ、ニレ、タモなどの樹木が眺望もきかないほど茂り、ナナツバ、ヨモギ、イタドリなどの雑草が2メートル以上も伸びている。まず、地味も申し分ないと見た。不便をいうならば石狩川を渡らなければ汽車に乗れないということである。隣の黄臼内には友成寿太郎の農場があって、この春から数戸が入植しているが、浦臼内には、開墾に従事している和人は1人もいないという。
―すばらしい土地だ―
月形に戻った安哉は、すぐに集治監用地189万坪の払下げを受ける意向を決め、北海道庁に行ってさし当たっての必要な手続きを済ませた。急いで東京へ帰る安哉の心は、すでに鉄石であった。
- 第四話
浦臼移住前後のもよう
翌明治26年3月、国会が終わるのを待ちかねて土佐へ帰ると、すぐに移住者の募集を始めた。当然ながら安哉の計画は、世間の注目をひかずにはおかなかった。いろいろな階層の人が北海道の土地を手に入れて移住者を入植させているが、キリスト教主義による理想農村の建設を目指し、自らも代議士の地位を捨てて、率先未開の原野に入るなどということは信じられないことであった。
~何も、代議士を辞めなくても~というのが選挙民の気持ちであった。にもかかわらず、安哉は夜っぴて経営要領を練ったり、郷里との連絡、賛助者の募集や、資金の調達に賭け回り、いたるところで「新農村建設の理想」を演説して歩いた。
第1回の募集は意外に成績が良かった。住みなれた暖かい土地を捨てて、寒さの厳しい蝦夷地へ移住する決心をさせたのは、いわば安哉への信頼からであったろう。だが、いよいよとなると、手続きや準備が思うようにはかどらず、肝心の農業用地貸し下げの許可が下りた時は、すでに6月に入っていた。北海道の半年は雪であるから、3月に入植して雪中に伐木を済ませ、雪どけを待って開墾、種まきをしなければ秋の収穫にはならないと聞いていたので、移住が遅れては1年を無駄にしなければならない。
ぶつぶつと不平を言う者も出たが、本格的な移住を1年延ばすことに決め、その代り、青年たちの中から先発者を出すことにした。
第1回の移住者としてまとまったのが26人、そのほかに県外から5人加わるはずである。これら20歳前後の青年が多い中に前田駒次が加わったことは、安哉にとってどれほど助けになったか知れない。安政5年生まれの36歳で、早くから自由党に加入していた前田駒次は本山外11か村の連合町村の助役を務め、実行力のあることで信望があった。安哉が駒次を自分の片腕として若い者の世話役としたことはいうまでもない。
出発の日が近づいた。東京に立寄る安哉はひと足先に陸路を出発し、土佐山組の長野和田吉弥、それに女房を連れた長野徳馬と和田佐吉を合わせて6人が6月27日高知丸で出帆する。続いて、前田駒次の引率する一行が7月1日、浦戸の港で江川丸に乗り込んだ。桟橋には親類縁者のほかに教会関係の者が大勢見送りに来た。動き出した甲板に並んで手を振る一行の中に幼児を抱いた石丸左右次の女房が、夫に寄り添っているのが人目を引いていた。
7月12日の朝、手宮駅から炭鉱汽船会社の汽車に乗る。安哉は、北海道庁に立ち寄るために札幌に行ったので、村山覚次郎が案内をかねて同行してくれた。汽車は、石炭を運ぶ無蓋車のため走り出すと石炭の粉が風にあおられて吹きつけ、眼を開けていられない。大騒ぎをしてコウモリ傘を広げたり、頬かぶりして後ろ向きに座った。
「幾10台の空車を連ねた列車が数珠のように機関車の走るとおりに、おとなしくついてくるのが見えた」と、始めて乗った汽車の思い出を、崎山久吉(後の久衛)は、このように語り、「崖の上、谷の間に土佐では見たこともない大きなイタドリやフキ、その他名も知れぬ雑草がバケ物のように茂っているのでびっくりした」とも話した。久吉は、まだ、18歳、一行にうちで一番年若であった。
汽車は、広い石狩平野に入り、札幌を通過したが、これが北海道の首都であることに気づいた者は少なく、江別まんじゅうを買って食べたことから江別だけは覚えていた。峰延に着いて汽車を降りる。これから先、月形まで16キロメートルは乗物がない。やむなく、大きな荷物を預け、差し当たって必要なものを背負ったり、棒を代わりにしてかついだりして炎天の下を歩きだした。囚人の作ったまっすぐな道だが、途中には家が一軒もなく、両側は茫々とした草原である。たちまち体じゅうに汗が流れる。その体臭をかぎつけて、クマバチのようなアブがうなり声をたてて追いかけてきて、着物の上から背中を刺す。瞬間、焼きつくすような痛みを覚えるが、そのあとかゆみが止まらない。草むらから無数のブヨが煙のように吹き出てきて、目や鼻に飛び込み、髪の毛にもぐりこんで食いつく。
あとでわかって残念がったことだが、もう少し汽車に乗って砂川で下車すれば、目的の浦臼まで12キロメートルなのに案内がわからずに、月形まで遠まわりしたのである。広い石狩川を渡船で渡り月形に着いたときは、日が暮れていた。宿は、キリスト教会の会堂で、池牧師や集治監に勤めていた同県人の山崎春江、永野義直らが来て何くれとなく世話をしてくれた。夕食のあとに、典獄の大井上輝前、教誨師の原胤昭、小野田農事指導員らも訪れて来て、歓迎の祈禱会を開いてくれた。繰返して歌われた讃美歌に、まだ洗礼を受けていない若者たちも胸を打たれた。
夜が明けた。いよいよ目的地への出発である。天坪出身の佐藤精郎は、その時の模様を次のように回想している。
13日早朝出発、今度は汽車だけでなく箱馬車に揺られ、亦々4里の道を運ばれ、午前11時に只今の農場サッテキに辿り着いた。道の幅は国道(増毛街道、現275号)であるから、かなり広いが、人馬の通うことが少なく、ただ1日1回郵便馬車が往復するだけで、馬の足跡と車の通じるところろだけが高草の間に穴のように見えている。途中2度も3度も大きな熊を見受けた。草の高さは車の上にいる我々の頭よりも高かった。
つづく
- 第五話
札的での共同生活
一行は、とりあえず札的内川にかかった橋の下の砂原に草を刈り集めて敷き、その上にウスベリを敷いて腰をおろした。もはや昼である。流れの水を汲んで御飯を炊き、軽食をすませ、前田駒次を中心にしてこれからの宿営方法を話し合った。
橋の近くに旅人のために造った「助け小屋」に、女と子供を入れることとし、あとは橋の下に寝ることにした。草を刈って敷きつめ、天幕を張る。ようやく日が暮れて寝につく。開拓地第一夜である。ところが、物凄い藪蚊の襲来である。眠れぬままに見える樹林の隙間から星がきらめいていた。
翌日、夜が明けるのを待ちかねて、あたりの探検を始めた。4,5人ずつの組を作って磁石を頼りに身の丈よりも高い熊笹、イタドリ、ヨモギの藪に分け入る。ナラ、クルミ、カツラ、タモの巨木が行手に立ちふさがり、集治監で切り倒した樹が横たわったりしていて歩行をさえぎる。熊が出るかも知れないというので、ワア―ッ、ワア―ッと大声をあげたり、そこらじゅうの物を叩いたりして騒ぎながら進んだ。それでも、熊に出会ってびっくりしたとという者もあり、磁石を持っていたのに方向を間違えて迷いこんだりした者も出たりして、夕食のときは、そんな話でもちきりであった。
その夜、これからの方針や生活についての心得を次のように話し合って決めたのである。
〇好きな土地を、5町歩自由に選んでよいこと。
〇来春3月に入植する家族を迎えるために小屋掛けして開墾に着手すること。
〇清教徒のアメリカ移住にちなんで農場の名を“聖園”とすること。
〇約束として酒を飲まないこと、日曜日には仕事を休んで礼拝すること。
が、主な内容であった。農場の事務についていえば、安哉が農場長となり、前田駒次が補佐、平井寅太郎が書記を務め、野口芳太郎が時には手伝い、それに月形の小野田卓彌が農事顧問という形であったし、久万沢佐一郎も何かと相談にあずかり、石丸夫妻が雑事や安哉の身のまわりの世話を引き受けた。
第2次移住者を迎えるまで
いよいよ安哉が事務にとりかかると、土地のこと、資金のこと、開墾や農具、生活必需品から教育、衛生のことなど、次から次へと仕事が出て、札的橋の上にむしろを敷いて道庁への報告書を作るのは容易でなかった。そこで材木を切り、札的内川のほとりに長さ14メートル、奥行9メートルの事務所を建てた。屋根は帆木綿で覆い、壁はオヒョウの皮を張り、床は地べたに割り木を並べ、その上に荒むしろを敷いただけのものであったから、寝るとゴツゴツと背骨にこたえた。彼らの自慢の一つは共同便所であった。根本が空洞になっていて一部がえぐれた状態のカツラの巨木を利用したもので、洞の中に溜めを掘り、20センチぐらいの間隔をおいて板2枚を渡し、穴の入口にむしろをつるした。入口が低過ぎるので1メートル75もある安哉は上体をかがめて入るのだが、姿勢を安定させるため、まず両膝に手をあてて、相撲の四股をふむ構えをした。“便所相撲”、安哉は、そう名づけておもしろがった。
炊事は、婦人たちに教えてもらい交代でみんなでする。おかずは、塩味か味噌汁が多く、小樽から仕入れた干ダラは御馳走の部類であった。
セリ、フキ、ワラビ、アイヌニンニクなどの野草は豊富だったが、アイヌニンニク(ギョウジャニンニク)を摂ると便所が強烈に臭かった。雨などで仕事を休んだ時には札的内川やオーエチャン沼でウグイやフナを釣っておかずにした。飲料水は秋が深まると、札的内川の水が涸れて、しまいには、ずっと川上の沢まで汲みに行かなければならなかった。
事務所ができあがると、次は自分たちの土地の選定である。好きな土地を選べと言われても、不案内の原野なので見当がつかない。「なるべく、近いところに集まれば熊に襲われる心配もないし、淋しくもないだろう」安哉はこう言って指導した。たとえば本山組は石狩川と浦臼沼の間にある中洲と呼ぶ地味のよさそうなところを選び、佐藤精郎ら5,6人は浦臼沼に沿った土地を選んだのである。小屋ができると次は開墾である。小屋のまわりとか、立木や熊笹の少ないところを選んで開墾し、収穫の早いソバや野菜を作り、秋には麦も蒔き付けた。
ところが、思いがけなくオコリ(マラリア)に罹るものが出始めたのである。樹林と湿地の中に粗末な小屋を建てて住み、過労と栄養不足が続き、そのうえ藪蚊とブヨに責められ通しの昼夜なのでマラリアにかかるのも当然であろう病人は仕事を休ませ、重い患者は月形の医者に通わせて手当をしたが、騒然となった。「寒さは覚悟していたが、マラリアのことは聞いていなかった・・・」という強い苦情も出た。27年の家族移住を迎えるまでに淋しく去った者もいたのである。しかし、農村出身の青年たちはこうした苦労にも屈しなかった。つづく
- 第六話
移住者も全員洗礼を受ける
小樽の牧師、光小太郎も聖園の事業に共鳴し、時々来訪しては安哉の伝道を授けた。その影響もあって、移住者の中から洗礼を受ける者がしだいに多くなり、10月8日に行われた洗礼式では、石丸左右次、和田吉弥、平井虎太郎、崎山久吉、野口芳太郎、畑山達三郎、佐藤精郎、水田菊太郎、それに北村宗信の9人が洗礼を受けたが、その後も入信する者があり、しまいには全員が洗礼を受けた。
恐れていた初めての冬が来た。11月の中頃から雪は容赦なく降り積もる。寒さは骨を刺すように痛い。1月になると、粉雪が屋根や壁のすき間から吹き込み、朝起きてみると、布団の上から部屋一面真白く積もっている。畳1畳ほどに切った炉に生木をくべるので、焚いても焚いても体は温まらず、生木がいぶって目を悪くする。部屋は煤で天井も壁も黒光りしている。こうして寒く、退屈な冬籠りが続き、4月になってやっと6キロメートル離れた於札内の駅逓所まで、新聞や手紙を取りに行くことができた。
名士の訪問者が相次ぐ農場
武市安哉と聖園農場の話は広く世間に知れ渡り、事務所を訪問する人も多くなった。明治26年8月の初めに、土佐の山内豊影候(土佐16代藩主豊範の長男)が将軍谷干城の案内で来訪するとの案内を受けた。
山内候は、谷の計らいで、安哉らの移住に対しても1万円もの大金を贈っている。
こうなると、事務所もあまり粗末なのでオーエチャン沼と浦臼沼との間にある高地に新築することとなった。移住者全員が総がかりで、札的沢からヤチダモ、キワダ(キハダ)などを角材にして運搬していたが、建築が終わらないうちに一行が到着したのである。
この日、安哉は月形に迎えに出たのであるが、一行は反対側の砂川から乗馬でやってきたのである。掘立小屋の事務所に迎え、ヤチダモの皮をのばし、ブドウづるを打ち付けた膳に、沼でとったウグイ、カラス貝を料理して出したところ16歳の山内候は、開拓地風の接待を珍しがった。安哉らが、あわてて月形から戻ってみると、一行は河原の上に座って、「国家のために大いに努力するように・・・」と話しているところであった。また、出迎えに
出た友成士寿太郎らの村の有力者に対しても、「武市がご厄介になります」と、礼を述べ、谷将軍も激励の演説をした。8月12日には、かねて安哉から招かれていた東北学院長の押川方義が訪ねてきた。この時には、新しい事務所が完成していた。安哉が押川を招いたのは、「開拓労働学校」を作るためで、宗教と労働と学問を統一した教育が目的であった。伊予(愛媛県)大洲の出身で、キリスト教の先輩、その上武士的で熱烈な愛国者として知られていた押川方義は乗り気になり、開校準備を兼ねさせるつもりで小樽の福井捨助という若い牧師を聖園教会の牧師として推薦した。安哉は、この計画をまだ青年たちには話してなかったが、土佐の山から出てきてここで5町歩の土地をみると途方もなく広く感じるに違いない。しかし、いまに狭いと思うようになるだろう。聖園を拓いたら、さらに広いところに出て行くんだね。そして、第2、第3の聖園を作ってくれ給え。まあ、ここは、そういう人たちにとって学校のようなものさ。
と、しばしば言っていたことからも、安哉のもくろみは想像できることであった。そして、安哉の考えを実現する人も後に多く出たのであった。
つづく
- 第七話
第2次移住者と聖園小学校創設
本格的な第2次移住者は明治27年の初めに札的に到着した。前田駒次ら家族らも到着した。
先発者たちは、家族を自分の小屋に迎え、その他の者はとりあえあえず事務所跡や「助け小屋」に分かれて住み、なお余った者は、集治監沢の入口にある集治監小屋に入った。集治監小屋は、5,6年前から樺戸集治監の囚徒が、増毛街道建設工事の際に泊まった大きな掘立小屋で、この沢を集治監沢と呼んだのはこのためである。農場は、にわかに活気づいてきた。土地の選定、開墾の準備が始まった。
新来者は、第1次移住者に案内されて土地を見回り、土佐山出身で鍛冶屋の門田善弥と、パン焼きの道具を持ってきた田岡森蔵は農場の中央部に入り、吉村吉太郎は増毛街道から南へ入った浦臼内川の近くに、前田千代松は、今の市街地のそばに、そして田岡寅太郎と大坪一道は草原、教育のある岡貞吉は浦臼沼のほとりというように落ち着いた。
また、ひと足遅れて8月に吉村吉太郎の父周吉が甥の谷悔浪に付き添われて到着した。
61歳の周吉は、耳からきた骨膜炎で余命のないのを覚悟してせめて自分のすすめで息子らを移住させた北海道を一目見て死にたいと思って来たとのことであった。どの家も、稼ぎ手が揃った。雪のあるうちに伐木をいうので一斉に伐木が始められて、続いて開墾が行われる。
蒔き付けが一段落すると、今度は小屋掛け、そして井戸掘りである。再び、開墾と作付である。
作物は、イナキビ、ハダカムギ、ジャガイモ、秋蒔ナタネが主で、イナキビ、ハダカムギ、ジャガイモは主食用として作られ、米はほとんど食べなかった。祝日に白米を3升か、精々5升買うぐらいもので、正月のモチ米もそんなものだった。当時は、大部分が無肥料だったが、それでも出来すぎて倒伏して困った。ジャガイモも1株で5升もとれたので5升イモと名づけられた。
イナキビは反当(10アール)8俵、ハダカムギ5俵、ナタネ8俵ぐらいとれた。換金作物と言えば、ナタネ、小豆などであった。冬期間造材の仕事が手近かに、いくらでもあったので、冬はこれに専念して、その収入とナタネ代で一家を支えていたようである。収入は少なかったが、一切無税で、生活も簡素だから支出は至って少なく、大自然にも恵まれて祈りと感謝をもって日々楽しく過ごした。聖日は厳守され、讃美歌の声は大森林にこだまして教会生活は部落をあげて全戸もれなく守られていた。
これは畑山翁の思い出である。
これら、第2回移住者の中には、20余人の学齢児童がいた。どのようにして子供たちの学業を継続させるか、親たちが移住の腹を決めるとき、まず心配したことの一つであった。
教育は1日もゆるがせにはできないという安哉の主張もあって、札的の元事務所跡に、大久保の手で建てた教会堂を一時小学校に兼用することになった。これが聖園小学校の始まりである。この聖園小学校は後に、太平洋戦争の終わり頃、軍部からの干渉で浦臼国民学校と校名を変更された経緯もある。つづく
- 第八話
明治28年(1895)、聖園農場に入植した田村楠衛は、昭和34年に開拓当時の思い出を『あら山時代』という小冊子にまとめて刊行した。その中に、同志をしのぶ詩があるので掲載する。85歳の作である。
今を去ること六十余年 南国の同志幾百人 夢を抱いて遥るばると 石狩平野の大自然 浦臼の地に移り住む 各々未墾地貰い受け 昼なお暗き原始林 まさかり振り上げ打ち込めば 木破(こっぱ)飛び交ふ木香は薫る 空を俺ふ大木も 地響を打ってどーっと倒る 倒れて青空晴ればれと アゝ晴ればれと 南国育ちの我同志 此所を墳墓の地と定め 木枝に雪の花咲きて 凍る広野に身を曝す 北風荒み吹雪く日も 毎日倒木に明け暮れて 至る所に倒木のこだま ザアークザアーク鋸の音 木を伐り枝切り山と積み 火の子あびつつ焼き払う いつか着物に煙り立つ アゝ煙り立つ 日曜毎に寄り集い(つど) 同志は互に励み合い 雪の融けるを待ちかねて 笹を刈りては焼き払う 荒地を起こし又削り 一心不乱に土地拓く 昼の疲れに良く眠りゃ 夢は千里の故郷(さと)がへり 熊も時々出没し 鉄砲かついで貰い風呂 夜は唐黍(とうきび)食い荒す 夜中に入り来る鼠の群れ 布団の上で相撲とる 頭や耳にかじりつく アゝかじりつく 不屈不壤の我同志 幾多の苦難を克服し 開拓苦闘幾星霜 広大なる密林も 豊饒の耕地と成し 進んで奥地を拓くもの 或は南米に移住して 同志の足跡偉大なり 今や同志は殆ど他界して 静かに眠る奥津城の 同志の冥福とこしえに
- 第九話
日常生活余話
農場で欠けているものの一つは医者であった。前年移住者たちがオコリに罹ってからはいっそう不安がつのり、幼児を持った母親たちの心配は大きかった。幸い、安哉の計らいで月形の監獄医務所長兼公立月形病院の荻原達彦(おぎわらみちひこ)院長が週2回事務所に来てくれることになった。これが浦臼の最初の医師であった。ほっとしたのもわずか数か月。
明治27年8月18日、同院長は補佐の雇医師守谷健之助と熱心に農家の診察を終えたあとオーエチャン沼に鴨撃ちに出かけて深みにはいって水死したのである。
しかし、翌28年、平井虎太郎の父溶吉が家族を連れて移住し、診療所を引き継いだ。オコリの診療には妙を得ており農場の人びとを喜ばせた。
27年6月農場事務所では、岡貞吉を主任として販売部を置き、日常必需品は月形や砂川にまで買い出しの必要がなくなり大助かりであった。その後、しだいに個人商店も出始め、岡貞吉も自分で雑貨商を営むこととなって農場の販売部は廃止された。
27年の収穫は大豊作であった。穀物は向こう1年分を確保することができて人びとは大喜びある。そのうえ、馬鈴薯、カボチャなどのなりものも驚くほどの出来ばえである。
この頃、かねて出願していた増毛街道沿いの150万坪と札的付近50万坪が許可となり、貸下げを受けた土地は全部で380万坪となった。貸下げ地は増えるし、作物は大豊作でホクホクしていたところが、10月に入ってまもなく突然の大雪があった。まだ、どの家も作物のとり入れはすんでいなかったし、燃料も薪も用意していなかったのである。このまま、来年の春まで雪に埋もれては大変だと、男たちは林に行って丸太のままで薪を担ぎこみ、女たちは、雪をかき分けて大根を抜き、そのあと晴天が続き、2,3日すると雪はあとかたもなく消えてしまった。
「あの時は、あわてたよ」人びとは、いつまでもこの時のことを思い出して笑い合った。
- 第十話
明治27年12月2日、日曜日の朝である。聖園教会では、福井牧師の説教が始まっていた。入口に人声がしたので教会員の一人が出て行き1枚の紙片を持ってきて牧師に渡した。
それを見て牧師の顔色が変わった。牧師はしばらく沈黙していたが、説教を続け、祈祷を終えてから壇を降り、会員の中から安哉の四男で14歳の武市精四郎を呼び紙片を渡し、ちょっと話したあと、よろめくような足どりで壇に登った。
「皆さんに、このうえもない悲しいお知らせをしなければなりません。武市先生が急病で亡くなられました」牧師の声はかすれ、精四郎はむせび泣いていた。何かあったなと会衆は感じとっていたが、牧師の説明を聞くうちに婦人たちのすすり泣きが起こり、やがて全体の号泣となった。
「そうか、先生が亡くなられたか。これから村はどうなるのか」人びとの口から洩れたことばであった。
武市安哉は、10月中旬、第3回目の移住者募集と、8月に亡くなった母のことで帰郷し、次女の時世と、外孫の土居基(ともに10歳)を連れて、東京、仙台を経て青森に到着、12月1日の午後9時に函館行きの千歳丸に乗船した。2人の女の子たちと旅のことを語り、合い眠りのついたのが、午後11時。翌2日午前6時、船は函館の港に入り、乗客は下船でざわめき始めたが安哉が起きようともしない。少女2人がしきりに安哉を呼び、傍らの乗客
もいっしょになって呼んだが起きないので、手をとってみると既に冷たく、そして息は絶えていた。
たちまち大騒ぎとなった。とりあえず遺体は定宿の角上旅館へ安置し、各地に電報を打って親戚、知人に連絡をとった。葬儀は仮葬と本葬の2回に分けて行われた。12月5日、午後2時棺は旅館を出た。信者で、札幌農学校第1期生の伊藤一隆が鼓笛隊を引率して先導し、聖園教会の福井牧師が枢旗を持ち、函館教会の栗原牧師、遺児、親戚、知己、市内の有志等多数に守られて教会に到着する。盛大で心のこもった葬儀は午後5時まで続いた。
翌日、午前8時、安哉の棺を載せた松前丸は、波静かな函館港から室蘭に行き、本葬は聖園教会で行われた。
墓標には、最初「吾れすでに世に勝てり」と書かれたが、その後自然石の墓標に「聖園創始武市安哉之墓」と書き、裏面に略歴を刻んだ。
つづく
- 第十一話
その後の聖園農場
武市安哉の急逝後、聖園農場の事業は、とりあえず三男の健雄(長男も次男も若死にした)が継いだが、まだ19歳の少年でまた体もひ弱なため、安哉の長女婦佐の夫である土居勝郎が後見人として実際の経営にあたることになった。武市家と農場関係者から頼まれてのことであった。婦佐は、「父は事務処理にうといほうでした。土居に目をつけたのは、そんな関係からと思います」と、勝郎が移住関係の仕事を手伝うようになった事柄について語っている。〈勝郎の人となりについては、第4編
行政「人物小伝」にて紹介〉
聖園農場に関係して間もない翌明治28年1月、勝郎は農場に隣接する未開地112万坪の貸付を受け、第3次住者400人を借り切りの船に乗せて、土佐の浦戸から室蘭に直航、3月初めに到着した。移住者の中には、小笠原尚衛などのキリスト教信者や、平井虎太郎の父で医者の溶吉などもいた。
農場本部は、勝郎を中心に再出発し、前田駒次、小野田卓彌、平井虎太郎らがこれを助け、外部から大久保虎吉、野口芳太郎、長野開鑿らが協力した。
農作物のうちで、かねてから問題になっていたのは水稲の試作であった。移住者を定着させる問題とも関連して安哉もかねてから考えていたことで、前田駒次にも頼んでいた。前田駒次はいろいろ手を尽くして、白石村の高橋某から新品種を入手して、黄臼内川寄りに入植している第2次移住者の水田菊太郎に頼んで28年播いてもらった。ほかに、杉村覚次も作ったという話もある。付近の湿地を水田にして播いたが、鴨の大群が来て、ひと晩で大半の種もみを食べてしまったため、秋にはいくらも穫れないと思ったところ、立派に結実したため農場に歓声があがり、翌年にはわれもわれと争って稲作を始めた。このため、厄介視されていた湿地が水田に変わって一挙両得になったわけである。大正9年(1920)北海道米作百万石記念祝賀会が行われたとき、武市安哉、前田駒次が表彰された。
進む開拓開拓は徐々に進み、移住者の生活も改善されて、28,9年頃になると、ストーブや風呂桶をすえた家が増えてきた。
29年には小笠原袈裟治がプラオを移入した。プラオの先に根切鉈を取り付けて馬に曳かせると、たいていの木の根はポンポンと切れるし、笹原も草地と同じように鋤くことができた。次第に他の農家も農機具を使用するようになり、馬に曳かせる整地用のハロー、フォーク、レーキなどの小農具もあって、開拓は急速に進みだしたのである。これらと同時に、耕馬も入ってきた。ところが、この馬は元来アメリカ系の改良馬だから、オーヨとかバイキなどの言葉が使われた。開墾したあとにはソバを播き、収穫すると打ったり、練ったりして常食代わりにしたり、玉蜀黍も引き割りにして食べた。
安哉の片腕であった前田駒次が、北光社農場設置のため北見に移ったのは明治28年である。北光社は、土佐の片岡健吉、坂本直寛、西原清東,沢本楠弥などの自由民権運動以来の人たちに、由比彦五郎、大脇勝吉、傍土定吉などを加えたキリスト教徒によって、聖園農場とほぼ同じような趣旨で創立された。坂本直寛が社長、沢本楠弥が副社長となり、人物手腕を見込まれて前田駒次が農場支配人として迎えられた。この前田駒次も、第4編の人物小伝に掲載したので本節では省略する。
つづく
- 第十二話
坂本直寛来場
安哉の没後、前田駒次や平井虎太郎、野村芳太郎の指導者が北見に移ったあと、明治30年聖園農場に有力な指導者である坂本直寛が一家をあげてやってきた。
浦臼沼北岸の小高い森の一隅に、ロシア風の角材を組んで積み重ねた二階建の家で、大きくはないが、日本座敷もあって、当時としては浦臼第一と言われた。(昭和29年頃、石狩川の治水工事で取り壊された。)
直寛は、安哉の遺志を継承して聖園農場の発展に取り組もうとやっては来たものの、明治31年の未曾有の大洪水の復興のために上京して救援資金の獲得に奔走したが、その後の処理で多くの試練に遭ったり、無牧時代の聖園教会のために大いに尽力したあと、明治35年には、政界と一切縁を切って、日本基督教会旭川教会に赴任した。その後、更に44年、旭川から札幌に移り、渡米不在中の北辰教会の教務を担当したり、後に朝鮮の龍山方面で伝道をしたりしていたが、44年9月、志半ばで死去している。土居農場の変遷と勝郎の実績
安哉が生存中は問題もあまり起きなかった農場も、入植者が多くなるにつれて複雑な問題が多くなったばかりでなく、安哉の考え方や、やり方に心を合わせていた人びとと、いわば大地主の旦那で、政治家肌、しかも事業家肌の人である勝郎との間に、農場管理についての意見の相違もしばしば起きるようになってきた。
聖園農場が土居農場と変わったいきさつは、主として資金関係によるものと思われる。古老の話では、29年に移住者の連帯保証で、東京の勧業銀行から金を借りたことがあるというくらいで、当時農場は資金難に陥っていたらしい。当初は100戸を入れる計画で出発したのだから有り得ることだし、安哉の死後、出資者との関係は順調でなかったらしい。そのため、28年春の第3次入植以後、土居自身が出資を余儀なくされるような事情にあり、これによって農場は経済的ピンチを脱することができたが、その額が嵩まった結果、ついに「譲渡」になったものと考えられる。崎山信義は、「ある自由民権運動者の生涯」にこう説明している。
そのためか、賃下げを受けた土地は第3次までで団体移住は打ち切られ、その後は単独入植となっている。したがって、現在浦臼内に住んでいる県外の人の多くは、明治40年頃以後に入ってきた人びとである。
土居勝郎は、私財を注ぎ込んで聖園農場の開拓を促進させたが、特に藤田卯之助、田村忠誠、三宮菊太郎と協力して養蚕の普及に力を尽くした。
聖園が一時北海道屈指の養蚕地となり、更に全道第一の養蚕供給地となった陰には、土居勝郎の功績がある。しかし、勝郎は、もともと政治好きであった。36年の道会補欠選挙では、財力、民権運動以来の政治歴、安哉の後継者という有利な条件で悠々と当選、4期10余年間継続して道議会員を務め、そのうち43年以降は議長の椅子にあった。その議長時代、札幌農学校の北大昇格に奔走して成果を上げている。
大正2年(1913)の秋、任期満了を持って道会を去ったが、その間、札幌に転住して、自ら農場を経営する暇はなく、農場本部は単に管理事務所に過ぎないものとなり、農場も普通農場同様に変わってしまい、日露戦争後の恐慌でますます不振となり、武市安哉が念願したキリスト教主義による理想農村の聖園農場、そして土居農場は42年5月には、北海道拓殖銀行に譲渡してしまった。
道会の任期を終えた勝郎は、一切を精算して上京後、高知に帰り、大正10年清貧のうちに病没した。信仰を回復して、平和な晩年であったという。
婦人婦佐は昭和26年に浦臼で死去、83歳であった。4男5女あったが、6人が早世、五女英子は36年間聖園教会の牧師を務め、三男洪郎、四男辰郎も牧師で、一家から多くの教職者を出している。
つづく
- 第十三話 – ①
武市か聖園か
浦臼町の村・町史は今までに3回発行されている。第1回目は、開村20年記念事業として、大正8年(1919)、2回目は敗戦後の昭和24年、そして3回目は、昭和42年発行の通称『70年史』と言われる町史である。
その中には、浦臼の農場について書かれているが、1回目と2回目には武市安哉の開設した農場を「武市農場」の名称を使っている。そして、3回目の町史では、これを「聖園農場」として取り扱った。
この「聖園農場」と呼んだことから論争が始まったのである。浦臼の歴史に一家言を持つ村田茂(故人)から「聖園農場ではなく武市農場ではないか」という意見が編纂委員会や町理事者に提出された。
その主旨は、「1回目、2回目で武市農場としているのに、3回目になってなぜ聖園農場とするのか。古い村史ほど、当時の人たちが考えていたことが書かれているのに、突然、聖園というのはおかしい」ということである。当然、編纂委員会や町理事者たちとも数回の交渉が持たれたが、意見が噛み合わず、話し合いは物別れとなり、結論的には、「次回町史編纂時の際には証拠を整理して決着を図るべきだ」となり、今回の百年史編纂まで約30年持ち越されたのである。
編纂委員会としては、この問題を冷静に受け止め可能な限り調査した結果「やはり、聖園農場とするのが正しい」と判断した。それは、明治33年の9月17日付で、北海道庁事業手「一色藤之助」の報告書に浦臼の各農場の内容があり、明確に「聖園農場」と記載されている。更に大正2年北海道農務部発行「北海道の農場」にも同様、聖園農場となっているので、編纂委員会としては、道庁説を採ったのである。
開拓当初、一般には「武市農場」と呼んだり、「土佐」とか、正式な届出名称など余り使わなかったため、第1回村史でも正式名称を使わなかったし、2回目もそのまま継承したものと考えられるし、第3回目の町史発行の際には、そのことにこだわらず「聖園農場」としたことからこじれたのではないかと推測されるのである。
つづく
- 第十三話 – ② 最終話
有限会社聖園農場の設立
武市安哉の「キリスト教主義による理想農村」を受け継ぐ者が絶えたわけではなかった。
昭和37年30日「有限会社聖園農場」が設立された。畑山・片山両家が中心となる極めて小規模な農場である。- 協業によって農場の近代化を進め生活の安定を図る
- キリスト教信仰による「神の国とその義を求め」主の僕として農民福音の業をこの地に求めたい。
との理由で、「主のある遠大なる理想に鑑み、主にあって永遠の生命の約束された者として、即ち主イエスキリストの贖罪によって与えられた御恩寵に、尊い厳なる感謝を表すため、信仰生活を基盤として礼拝を厳守し、教会の徳を立て以て伝道の業に励み、身をもって主の証人となりつつ農場の近代経営を図り、生活の安定を確立し、自らの生活は純潔をもってし、真の文化を築き上げて社会に貢献すると共に、武市安哉の理想を顕現すること」を目的としている。
初代代表取締役には畑山勝盛が就任し、40年には水稲経営20町歩5か年計画を樹立し、この年5町5反を開田、43年には、1戸加入し3戸法人とし、45年1法人と2戸で札的大型機械利用組合を設立、47年第2代表取締役に片山常雄が就任、48年1戸脱退、55年1戸で生しいたけ生産組合を設立、57年には創立20周年記念誌を発行、63年第3代代表取締役に畑山勝敏が就任、平成元年農場内に稲作部門と畑作部門を新設、平成9年構成員1名加入で現在に至る。
平成10年現在、構成員男4名女3名、従業員1名、夏季雇用3名、そのほかに子供を含め家族9名をかかえ、資本金888万円、水田自作地17.1ヘクタール、貸借地16ヘクタール、宅地71アール、そのほかに住宅、農業倉庫、施設ハウス、ライスセンター、コンバイン格納庫(共同利用)をもって、水稲、畑作、野菜等の複合経営を行い、100年前に創立された「聖園農場」の精神を生かした希望ある活動を続けている。完
約1年半にわたり連載をして参りましたが、この13話―②をもちまして、終了と致します。
ご愛読ありがとうございました。浦臼町の皆様、ありがとうございました。